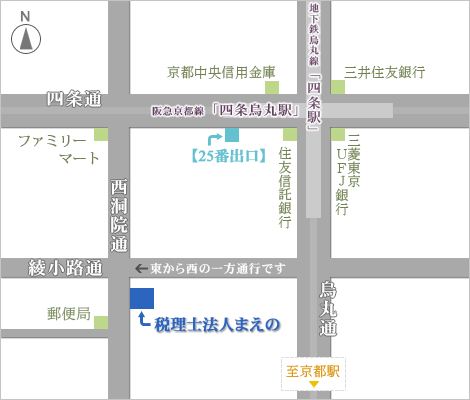新年あけましておめでとうございます
みなさま 穏やかなお正月をお過ごしになられましたでしょうか
普段の延長のちょっと長いお休みを過ごした といったお正月になってきていますが
やはり空気がすがすがしく感じられます
いよいよ今日から社会が動き出します
もう明日になれば 普段の生活にどっぷりつかってお正月も忘れてしまうのか という気がしないでもないですが
悪馴れしないで 気持ちは清く 新しい気持ちで一歩を踏み出したいものだと思います
今年は何ができるか 何をしようか 楽しい明日を頭に描いて毎日を過ごそう そう思っています
今年もどうぞよろしく御願い申し上げます